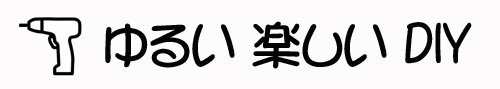DIYで何か製作したり修理をするとき、市販品で対応できないパーツを自分で作れたら理想的ですね。
苦手なイメージだった3Dプリンターですが、無料のモデリングツールとコスパの良い3Dプリンターを入手したら、意外と簡単、プリントデビューできました。
はじめる前のこと‥
きっかけはプラケース
ある時、電子基板を組み込むプラケースをネットやお店で探しましたが、サイズや形がピッタリなものに巡り合えません。
3Dプリンターなら好きなように作れるとは思うのですが、マニアックなイメージを持っていました。
冷やかし半分で、3Dプリンター事情を調べてみると‥
・価格が3~5万円程度の機種で十分活用できる。
・マニアックさを印象づけていた設定や調整が、かなり自動化されている。
・無料で高機能な3Dのモデリングツールが使える。
・材料のフィラメントは1㎏3千円程度で、ランニングコストは気にならない。
これはもう、すぐに始めた方がいいレベルですね。
Tinkercad(ティンカーキャド)で初めてのモデリング
とはいえ、プリンターを使う前に、果たして素人にモデリングができるのか‥
とりあえず、手軽に体験できる「Tinkercad(ティンカーキャド)」という無料のツールを使ってみました。
インストールせずブラウザ上で使えるので、ちょっとやってみるには好適。
操作も直感的で、積み木を組み合わせるようなイメージで形が作れます。
【Tinkercadのトップ画面】

Tinkercadで、試しに四角いプラケースに挑戦したら、意外に簡単に出来てしまいました。
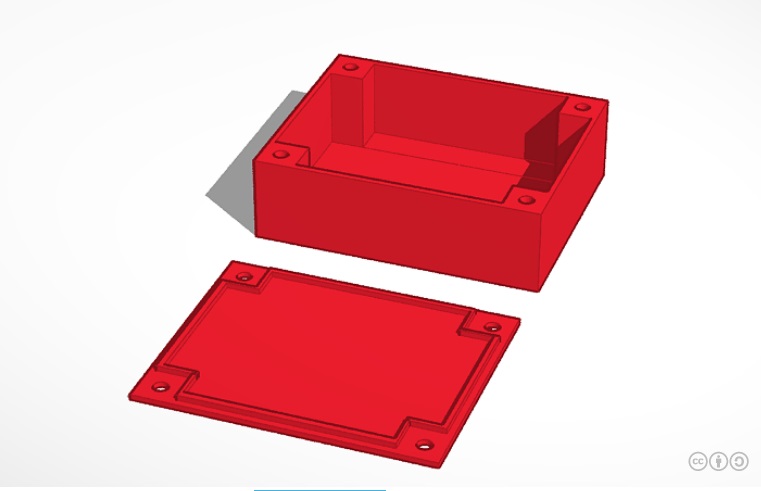
基本は、ブロックを足したり引いたりして 立体の形を作っていきます。
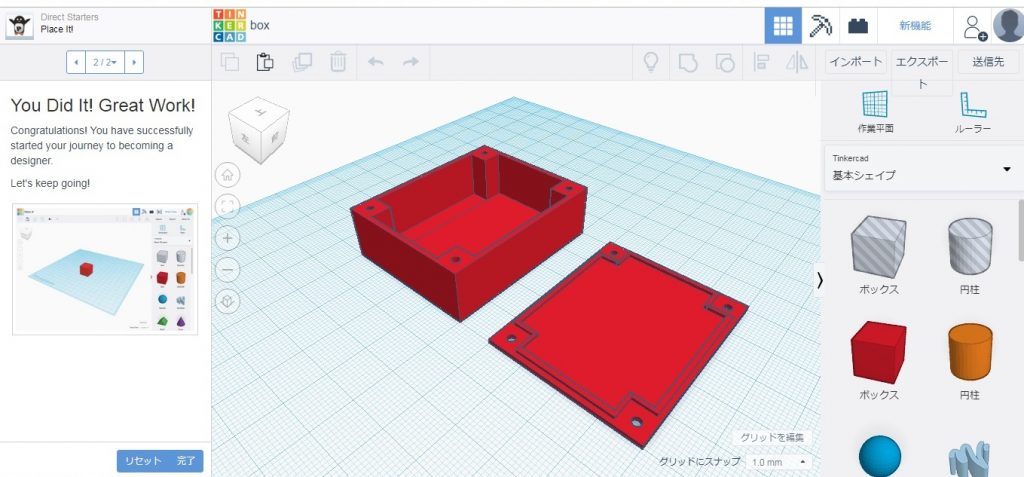
右側の基本シェイプからドラッグ&ドロップして作業平面に置き、寸法を決め、小さい寸法の空洞ブロック(グレー)をはめ込む式で立体モデルを作ります。
細かい細工も簡単で、四隅にフタをねじ止めするための穴も付けました。
丸い箱は、単純でもっと簡単でした。
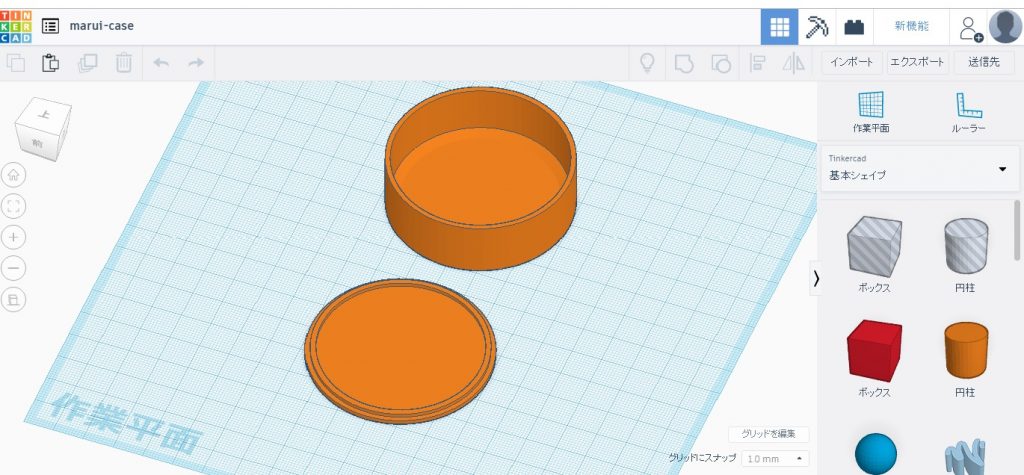
モデリングができると、実際にプリントしたくなりますね…
手に入れようとする3Dプリンターは、進化の途上。
価格がこなれて性能の良い機種が続々と出るのでしょうが、待っていてもキリがありません。
前のめりな気持ちのときに買ってしまいましょう‥ ♪
いよいよ始めるぞ3Dプリンター
価格や扱いやすさで目星をつけておいた3Dプリンターは、ANYCUBIC MEGA-S。
アマゾンで34,999円でした。
組み立てとヒートベッドのレベル調整は、自分でやる必要があります。
組み立てはとても簡単
届いたANYCUBIC MEGA-Sの中身一式。

3Dプリンターはかなり大きな図体なので、輸送のためには組み立て式にするのが合理的なのでしょう。
必要な工具も付いていました。

本体とフレームを数本のネジで止めて、あっけなく組立て完了。

ノズルとヒートベッド(台)の隙間は「紙一重」
3Dプリンターは、ノズルとヒートベッド(台)の間隔がとても重要です。
隙間が広いと、ノズルから押し出されたフィラメントがヒートベッドに定着しにくい。
逆に、隙間が狭いとノズルがフィラメントを押し出しにくく、また、描いた線を引っ掻いてしまうようです。
MEGA-Sはリーズナブルな製品で、隙間の自動調整機能は搭載されていませんでしたが、モデルチェンジがあれば、価格は変わらず自動化されるでしょう。
手動で調整するMEGA-Sの場合、1枚のコピー用紙を使います。

ヒートベッドの上にコピー用紙を1枚置き、ノズルとヒートベッドの隙間が紙一枚の厚みになるよう、ベッドの四隅にある高さ調整ネジを回します。
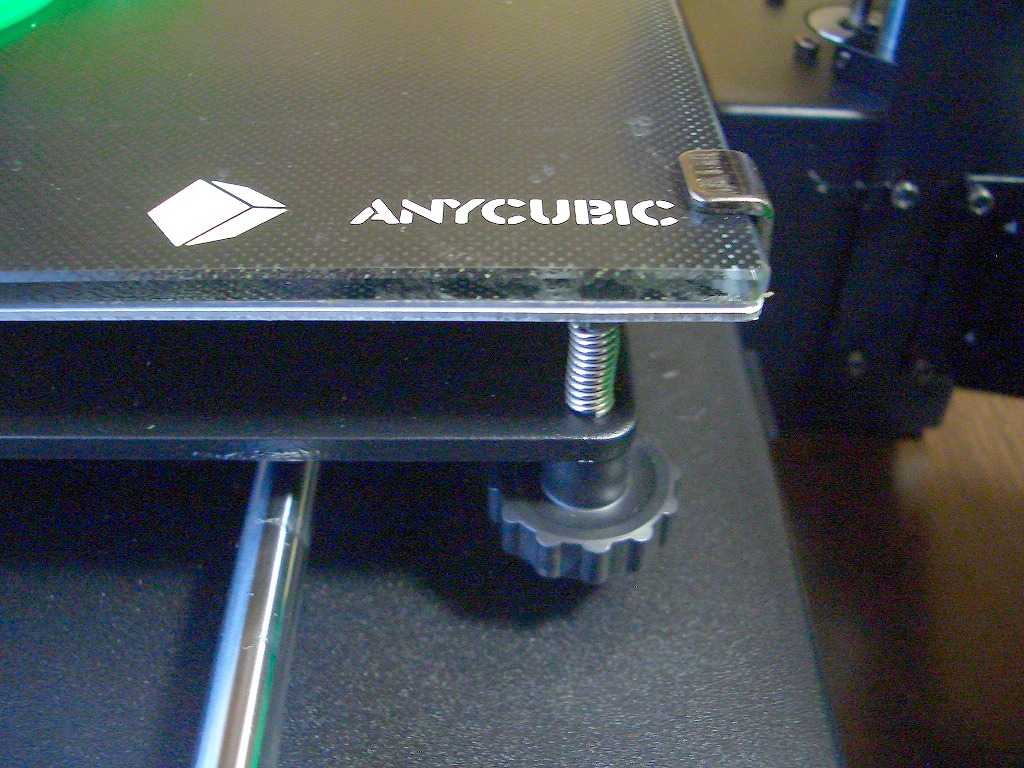
ノズルとヒートベッドを水平に移動させながら、紙を引っ張ったときのやや重い抵抗感が、どの位置でも同じになるように調整します。
サンプルデータでテスト
調整が済んだら、付属のサンプルデータでテストプリントしてみます。
スタートして第1層目をプリントし終わったところで中断し、きれいな板状になっているかどうか確認します。
スクレイパーではがしてみると、
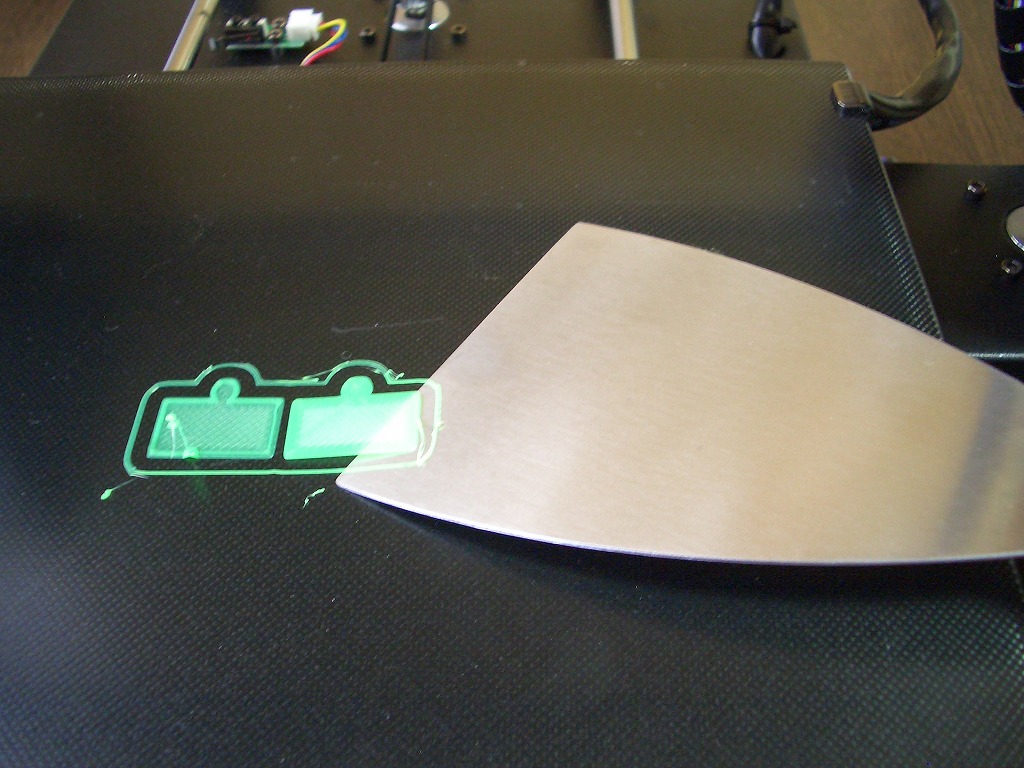
これは失敗。
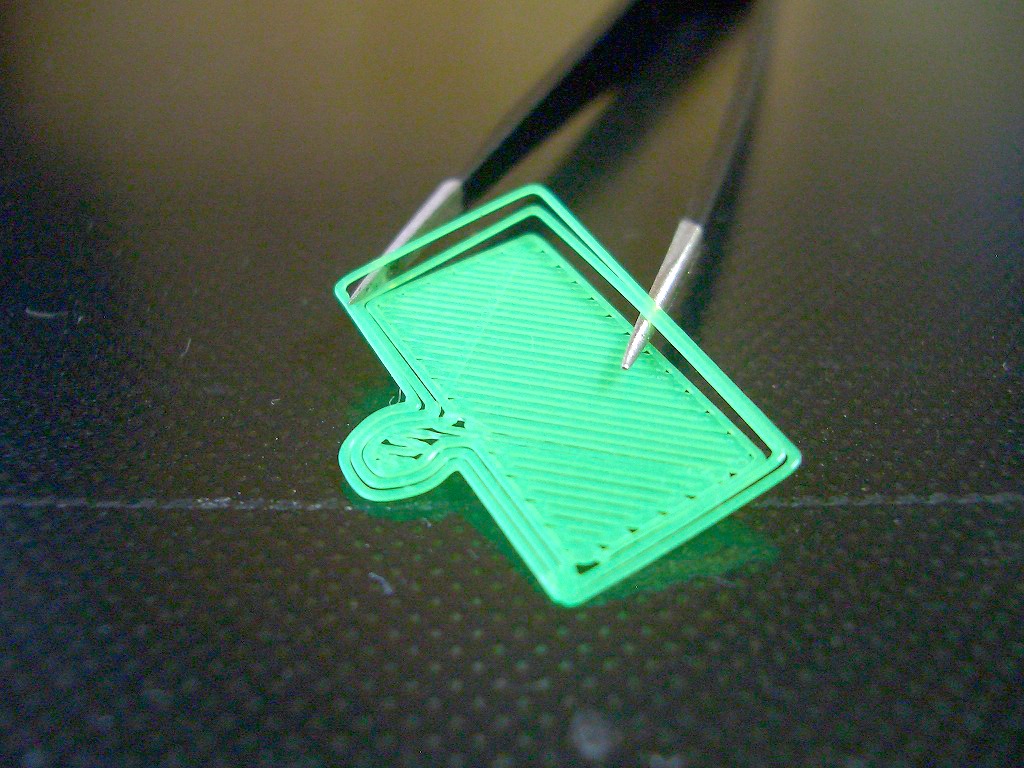
ノズルとベッドの隙間が広すぎ、融けたフィラメントが横とくっつかずにバラバラです。
適正な隙間なら、フィラメント同士がくっついて板になるはずです。
調整ネジで隙間を詰めていき、3回目はきれいな面ができました。
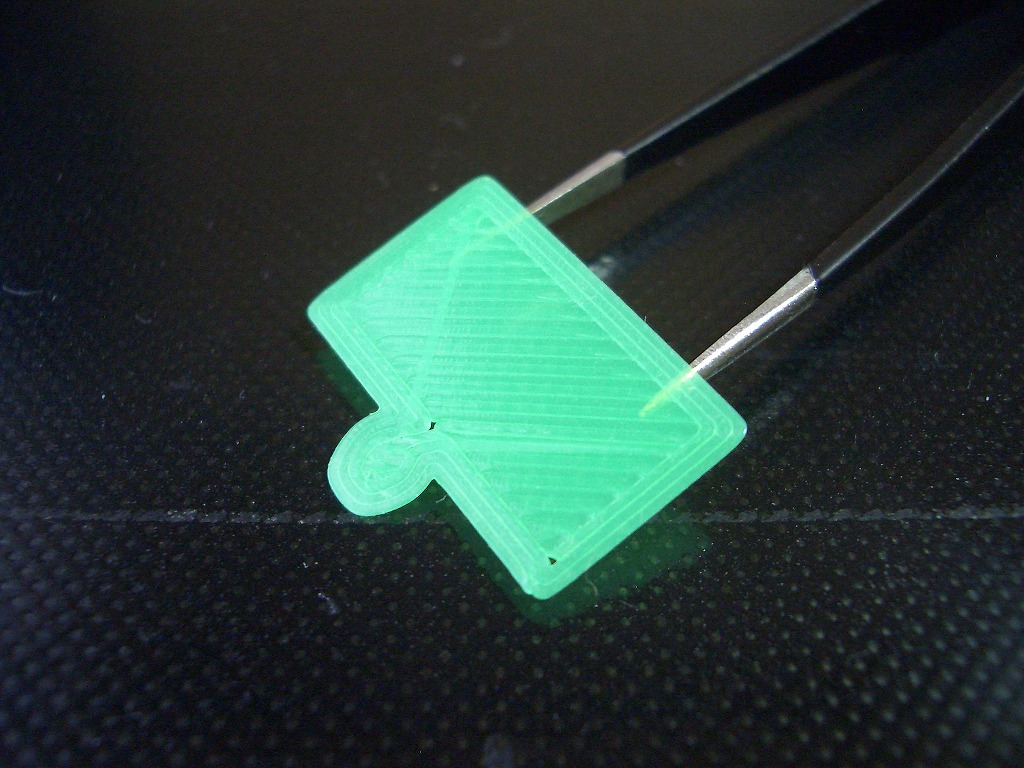
文字どおり、成否は紙一重 ♪
結構めんどくさい調整なので、自動化されれば随分扱いやすくなります。
でも、自分でやってみると、プリント成功のキモの部分というのがよくわかりました。
感動のプリントデビュー
立体のモデルを ひと筆書き のデータに変換
モデリングした3Dのデータは、そのままではプリントできません。
Tinkercadで作ったSTLファイルを、「Cura」というスライサーソフトで3Dプリンター用のGcodeファイルに変換してから3Dプリンターに入力します。
つまり、3Dモデル(STLファイル)を、3Dプリンターが ひと筆書き で描けるよう一層ずつにスライスし、その描き方を指示するGcodeファイルに変換するのです。
Curaは無料で使え、日本語化もされています。
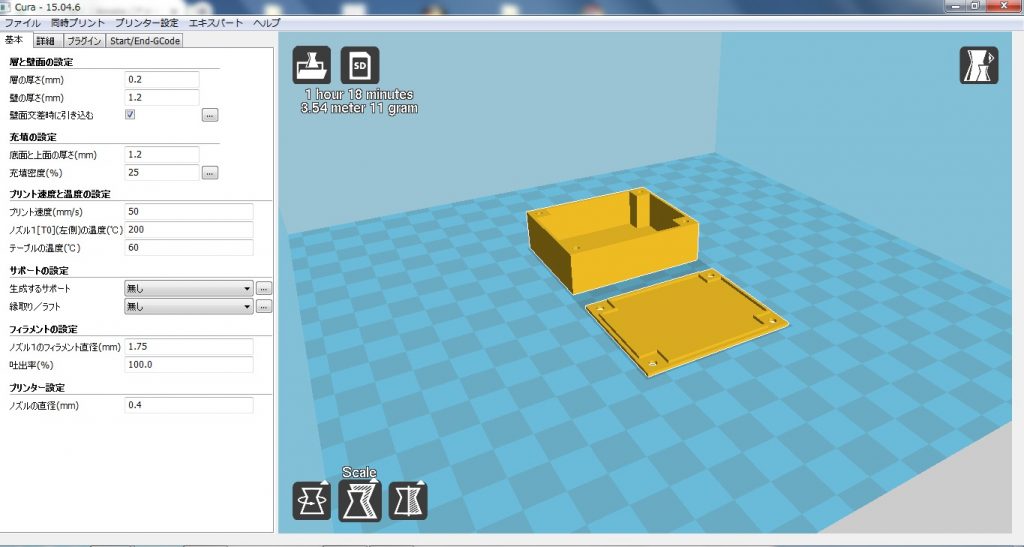
3Dプリント開始!
Gcodeファイルを入れたSDカードをプリンターに挿入し、取説どおりに準備したらスタートします。
さあ プリントデビュー♪
ヘッドが動き出す時のわくわく感はなんとも言えません。
ヒートベッドが前後に、ノズルが左右に動きながら、一層づつ描き重ねていきます
規則正しく動いたかと思うと、急に意外な場所に移ったりするので「なんでだろー」と思いますが、出来ていく形を見ると、「そうか、そういう訳ね…」と、計算された動きに納得させられます。
ノズルの動作を決めるスライサーソフトって、凄いですね。
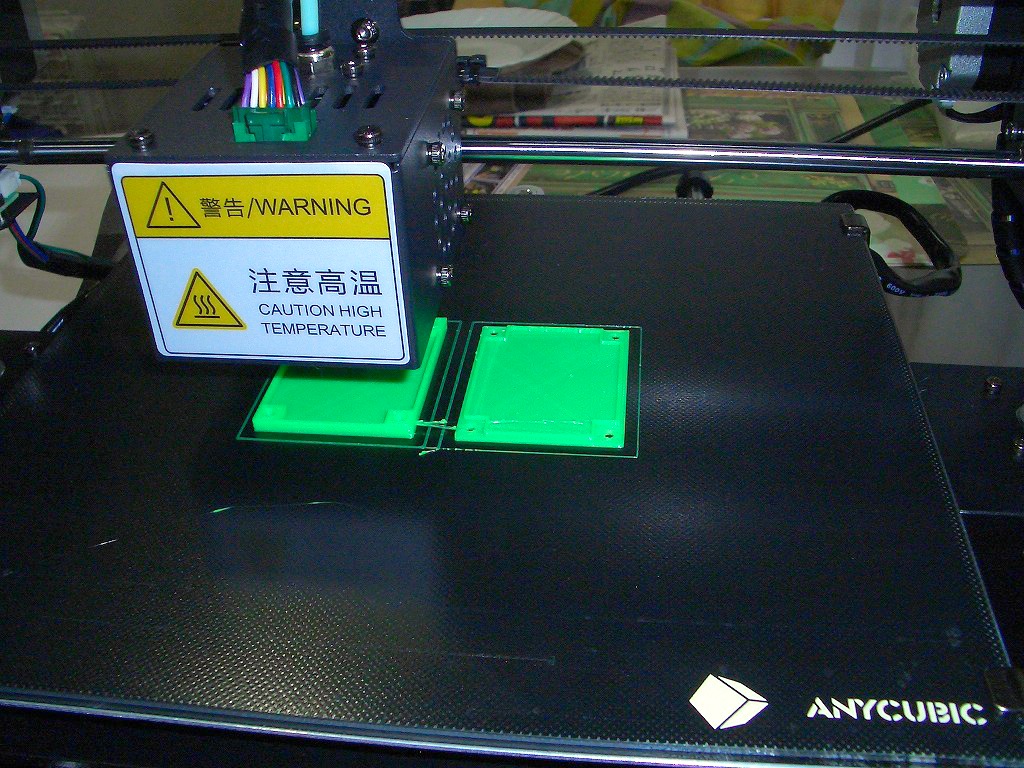
しかし‥
プリント時間が恐ろしく長い。
4㎝×5㎝×1.5㎝のこんな小さな箱なのに、完成まで1時間20分かかりました。
ひと筆書き方式なので仕方ないですね。
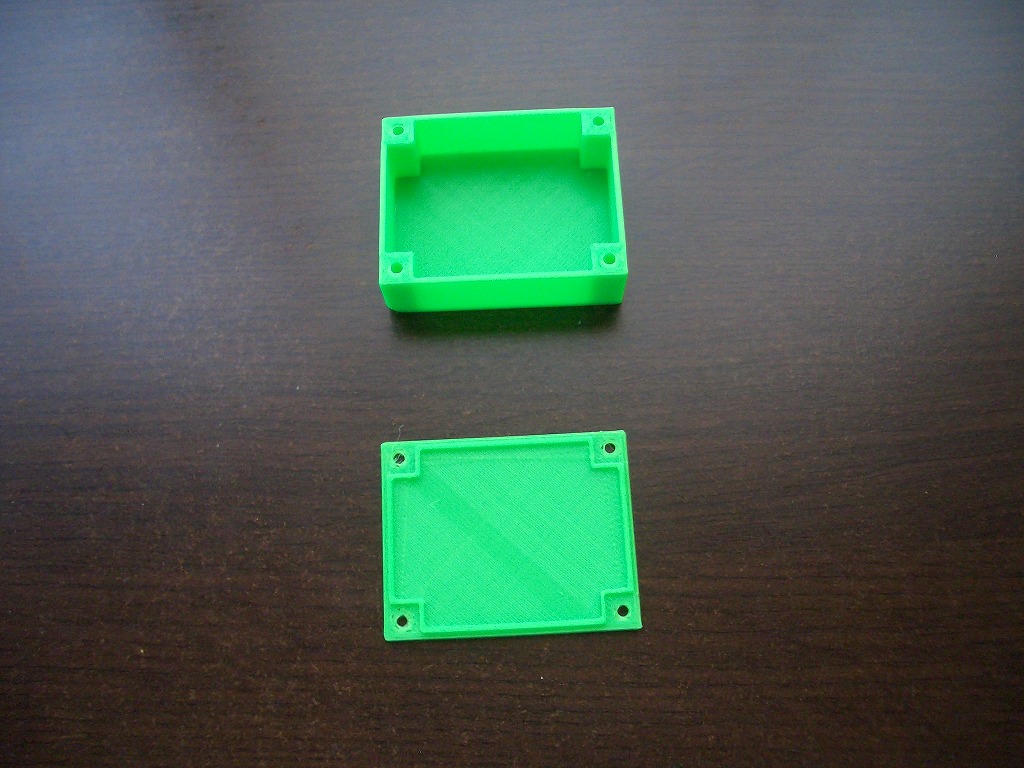
結構、蓋が良い感じにはまり、爪の先でパカッと開けることができます。
ついに初心者の仲間入り。
気をよくして、丸いケースもプリント。

こちらもフタがピッタリ。
なんだか、
先が楽しみになってきたぞ…♪
まとめ
3Dプリンターのはじめの一歩を踏み出しました。
モデリングや3Dプリンターの扱いは思っていたより簡単で、単純な形のものはすぐに作れます。
これからDIYに応用するには、複雑な形が描けるようモデリングの腕を上げないといけません。
モデリングが自在にできるようになれば、3Dプリンターも高速で高性能なものが欲しくなるでしょうね。
いろいろ、楽しみが膨らみます。

MEGA-Sでは苦労してレベル調整したんですが、後継のKobra2 Neoはオートレベリング機能を搭載していて、簡単に調整できるようです。
それに、印刷スピードも5倍に速くなっているなんて‥
買い替えを意識してしまいますね。